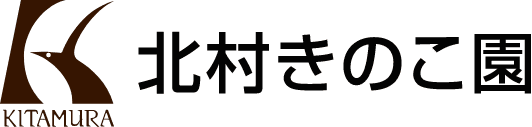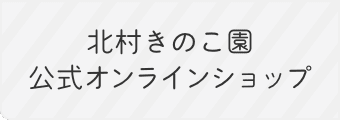きのこ通信
コラム 季節の変化を楽しもう
日本はありがたいことに四季があります。
地域によって季節の変化は様々ですが、春には桜や菜の花など草花を楽しみながら新緑の季節を迎えます。
雪解けの後はあたたかな陽気と共に人の生活はアクティブになります。
暑い夏には、海水浴を楽しんだり暑さをしのぎながら穏やかに暮らす方法を身につけてきました。
秋には木々の色付きを楽しみながら食物の豊かな恵みに感謝し、来たる冬に向けて体も心も準備を始めます。
冬は、寒さと共存しながら保存の効くものを仕込んだり、雪や寒さを利用した生活を行ってきました。
四季を楽しみながら、季節の変化を上手に生活に取り入れながら先人たちは豊かに暮らしてきました。
旧暦を用いていた頃の日本では、月の形や太陽の動きをみながら祭事を行ったり二十四節気を併用することで、より深く季節を理解しそれぞれの時期を味わってきました。
二十四節気は4つの季節をさらに細分化し、それを元に人は農作業を行い、日々の生活を豊かに彩ってきました。
技術の進歩と共に手作業で行われていたものの機械化が進み、野菜なども季節を問わず一年を通して味わえるようになり、以前に比べると季節感を感じにくくなってきていますが、日本古来行われていた生活様式であったり、行事ごと、旬を大切にするなど見直されつつあります。
自然を感じ、自然を味わう昔ながらの生活を知ることで、心豊かな毎日が送れるはずです。
二十四節気と共に今の時期をしっかり味わうヒントになればと思っています。
ちょうど、5月目前の今の時期は、二十四節気の穀雨(こくう)といい、たくさんの穀物を潤す春の雨が降る頃のことをいいます。
春の雨は、作物にとっては恵みの雨です。
この穀雨が過ぎると、夏の始まりを告げる八十八夜(はちじゅはちや)が訪れます。
八十八夜とは、春の始まり立春(2月4日頃)から数えて88日目の夜を八十八夜といいます。
季節の移り変わりの目安となる一つです。
日本の唱歌「茶摘(ちゃつみ」にも「夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が茂る・・・」とあるように、八十八夜を迎えると夏がそこまで来ているとうたっています。
ちょうど、八十八夜は5月2日頃になります。
八十八夜には新芽を摘んだお茶を飲むと長寿になると言われています。
ちょうど穀雨の時期は、春の土用の時期と重なります。
土用と聞くと、夏のイメージが強いかもしれませんが、土用は年に4回おとずれます。
土用とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間を指します。
特に春のこの時期は、気候も一気によくなり陽気な気持ちにもなりますが、新天地での仕事・学校と環境の変化もある時期なので非常に疲れやすく、寒暖差もあるため胃腸を壊しやすい人が増えます。
夏の土用にはうなぎを食べるといいと言われ実践されている方も多いと思いますが、この春の時期は、よもぎが良いと言われています。
よもぎは、寒性で消炎作用に優れ、止血であったりお灸で使われることがあります。
利尿作用があるので、この時期胃腸を壊しやすい方にぴったりです。
体内に水分が貯まりやすくなると体がむくんだり、だるさを感じる人が多くいます。
よもぎを摂ることで利尿作用が期待できむくみに効果があります。
生ではなかなか食べられないので、よもぎ餅やよもぎ茶として召し上がってみてください。
その他、この時期には新ごぼうや、鯵(アジ)、サザエや山菜のこごみなどが旬を迎えますので、旅先の産直市場などで見掛けられた際には購入されてみてはいかがでしょう。