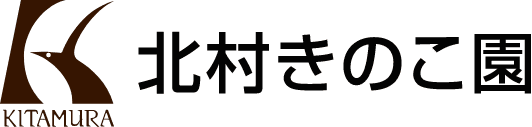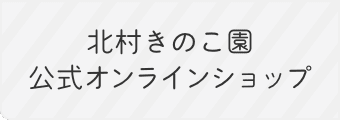きのこ通信
お役立ち食材でつくろう!「ライスペーパー巻き巻き」
今月のお役立ち食材は、「ライスペーパー」。
今月Voiceのコーナーで、Yさんがライスペーパーを使ってエリンギィピザを調理してくださっていたのを拝見し閃きました。
今、ライスペーパーのお料理が流行っているとか・・・・・。
流行に乗り損ねてしまいましたが、今からでも遅くありませんよね。
とてもおいしく仕上がりましたので、皆様にもご紹介したいと思います。
ライスペーパーとは名前の通り、お米を使って作られたベトナム料理の食材です。
よく生春巻きの材料として使われています。
現在では米粉やタピオカでんぷんを使っているものが多く、もちっとした食感も一緒に味わえます。
タピオカでんぷんを使うことで、1枚を薄く仕上げても破れにくくする効果もあります。
ライスペーパーを水で戻して使うことで、中の具材が透けてみえ、彩り次第でみた目も楽しめる一品になります。
ライスペーパーは水やぬるま湯を使って戻します。
濡らさずそのまま食材を包み込むことはできません。
ただし、長時間水やぬるま湯に浸しておくと柔らかくなりすぎて、破れたり、皮がくっついて食材を包むことができなくなるため、ちょっと硬いかなと思う範囲で止めるのがポイントです。
サッとライスペーパーの両面を水に潜らせるくらいで十分です。
具材を入れて、巻き込むことで見栄えの良いお料理が完成します。
最近では、食材をライスペーパーに置き換え、カロリーを抑えるレシピも提案されています。
原料がお米でできているので、糖質はありますが、ジュースやお菓子、パンに比べると血糖値の上昇はゆるやかで、エネルギーとして消費されやすいので、適量であれば太りにくい食材でもあります。
ライスペーパーを単体で食べることは少なく、野菜や海鮮など様々な食材と組み合わせて食べることにより、一品でバランスよく食事をすることができます。
原料が白米なので、他の炭水化物に比べ消化吸収に時間がかかるため腹持ちするのも魅力です。
ライスペーパーの糖質が気になる場合は、血糖値の上昇を抑えるマグネシウムを多く含む食材「きのこ類」を一緒にとることで、緩やかになります。
糖の吸収を抑えるビタミンB1を多く含む豚肉や、魚類なども一緒に包んで食べるのもおすすめです。
食材が用意できていれば、サッと水に浸して巻いて食べることができるので短時間で食事の準備をして食べることができます。
お米にはグルテンが含まれていないので、小麦を控えている方にもぴったりです。
生春巻きはもちろん、フォーのようにライスペーパーを麺に見立てることもできますし、餃子の具材を挟んで焼いてもいいですし、Yさんのようにピザの生地としてもソーセージの皮にしても美味しいです。
友人が、クリームコロッケを作る際にライスペーパーを使うと具材が飛び出すことなくあげることができると先日おすすめしてくれました。
フルーツやクリームなどを包んで、デザートなどにすることもできますし、アレンジは自在!
ぜひ色々と挑戦してみてはいかがでしょうか。
<材料>
ライスペーパー、エリンギィ、なす、大葉、鶏胸肉ミンチ、塩麹、ナンプラー、米粉(片栗粉)、粗びきこしょう、ごま油
<作り方>
1 エリンギィ、ナス、大葉はみじん切りに。
エリンギィは食感が活きるように今回は芽とりエリンギィを使用。
食感が感じられるようあまり細かく刻まない。
2 ボウルに1と鶏胸肉ミンチ、塩麹、ナンプラー、米粉(片栗粉)、粗びきこしょうを入れ、全体を混ぜ合わせる。
塩麹を効かせるため、30分ほど置いておく
3 ライスペーパーに水に潜らせ、まな板の上におく。
その上に、2の具材をおき、具材を包み込むようにしっかりまく。
4 フライパンにごま油ひき、3を入れ両面を焼き上げる。
ライスペーパーを水で戻しすぎるとくっつきやすくなるのでちょっと硬いくらいで包むことがポイント。
5 焼き色が両面についたら、出来上がり。
短時間で完成し、尚且つおいしくできます。
夏の時期に収穫できる食材を一緒に包み込んで焼き上げるのがポイント。
今回はナスや大葉を入れ込みましたが、オクラやピーマンなどもぴったり合うと思います。
ナンプラーを入れることでエスニックぽさも感じられます。
小さなお子様にはナンプラーの匂いが気になるかもしれませんが、大さじ1ほどですので、気にならないようです。
熱々を食べても、少し冷めてから食べてもおいしく召し上がっていただけます。